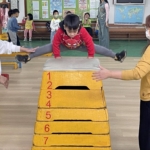保育園に入園するということは、さまざまな家庭の子どもたちが集まる小さな共同体に入るということであり、子どもたちはそれぞれ違った個性を持っている。しかし、幼稚園であろうと少人数クラスであろうと、子どもはまだ周りの環境について無知であり、毎日経験することは「遊び」である。 年中・年長クラス頃になると、子どもの認知能力も向上し、運動能力も向上してくるので、もはや情報を受け取るだけの受動的な存在ではなく、積極的に探求し、知識を得て、知識欲を満たしたいと思うようになる。
幼稚園が終わると、子どもたちは生まれて初めての卒園式を経験し、先生やクラスメートとの別れに直面し、小学校に進学して新しい環境、新しい先生、新しいクラスメートを知ることになる!5歳、6歳、7歳の子どもたちには、もはや幼児と同じように接することはできないが、あまりに無邪気で生き生きとしているため、親は彼らをどう導いていいのかわからなくなることがある!
この時期の子どもたちを理解するのは難しいことではない。 一番簡単な方法は、私たちが小さかった頃、大人からどのように世話され、扱われたかったかを考えることだ。それが子どもの考えであり、簡単に言えば、3つのレベルがある:
注目されたい:子どもは誰でも親に愛されたいと思っており、脳は「愛」を親の気遣いや注目と認識する。 そのため、子どもは親の前での振る舞いを楽しむようになり、物を捨てるなど悪いことをしていても、親に叱られることを「注目される」と脳が解釈するようになる。これは、私たちが子どもの考え方を大人の視点から判断することが多いからだ。実際、子供のやんちゃな行動に対処する最善の方法は、それを無視して子供の行動をこっそり観察することである。 子供が正しいことをしている限り、大人はその子をたくさん褒めてあげるべきである。そうすることでしか、子供は「注目」や「賞賛」を得られる行動とは何かを学ぶことはできないのである。
肯定されたい:学習や対人関係に直面し、子どもたちの生活は幼い頃のような単純なものではなくなった。
子どもの欲求不満耐性を高めるには、欲求不満と向き合うだけでなく、達成感を積み上げて欲求不満に挑戦する意欲を高めることである。 そのため、子どもはあらゆるところで肯定を求めるようになる。最も多いのは、学校で学んだ知識を親に「披露」したり、優秀な成績を親に伝えたりするようになることである。しかし、子どもは親が一番忙しいときや、親が一番疲れているときなど、いつもタイミングを選んで親のところにやってきます。 母親が子どもにはっきり話をさせなかったり、気軽に追い払おうとしたりすると、子どもに心理的な悪影響を与え、親子関係にも影響を及ぼします。子どもが些細なことを話してきたときには、その場しのぎの返事をするのではなく、別の方法で肯定感を与えてあげましょう。 例えば、「今話していることはあなたにとって大切なことだけど、ただ話すだけではダメなんだよ」とリラックスさせてあげたり、今話したことを絵に描いてもらったり(幼稚園児の場合)、書いてもらったり(小学生の場合)して、子どもの絵や書いたものを集めておける場所を探してあげたりするのもよいでしょう。これは子供が認められたと感じるだけでなく、成長の記録にもなる!
理解されたい:発達の観点から見ると、5歳を過ぎる頃から、子どもは徐々に「自己中心性」を捨て、「共感性」の形成の始まりである、すべての人の感情の動きに気づき始める。また、「自分のことは親が一番よく分かってくれている」「何も言わなくても親は分かってくれるはずだ」と考えるようになる。小学校に入学すると、勉強面でも対人面でもプレッシャーがかかるため、家に帰ってから親にすべてを話すことができなくなる。 したがって、子どもが退屈して帰ってくるのは、必ずしも親に腹を立てているからではなく、その時の子どもの感情によって親に状況を話すことができないのである。説明を求めることに躍起になりすぎるのは、子どもにとってストレスの元となり、親は自分のことを理解してくれていないと子どもに思わせることにもなりかねないからだ。
子どもが自分を傷つけるようなことをしない限り、静かにさせたり、泣かせたり、騒がせたりする!子どもの感情が安定するまで待ってから、子どもと「コミュニケーション」をとる。 子どもの不適切な感情行動を理解するだけでなく、子ども一人が怒っても問題は解決しないこと、子どもが怒ったからといって親は何が起こっているのかわからないことを子どもに伝えることが大切である。 そのため、例えば、子どもは自分の感情を吐き出すために部屋に行き、感情を吐き出した後に親と話をしに戻ってくるなど、お互いに理解し合う方法を話し合うことも可能である。良いコミュニケーションは、親が子どもを理解するのに役立つだけでなく、子どもが自分の考えを親に伝える方法を知るのにも役立つのである。続く
張旭暉先生、児童作業療法士